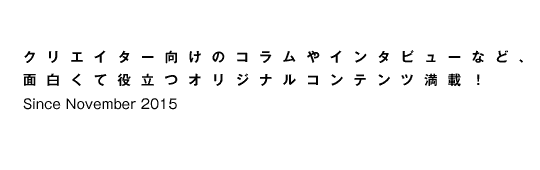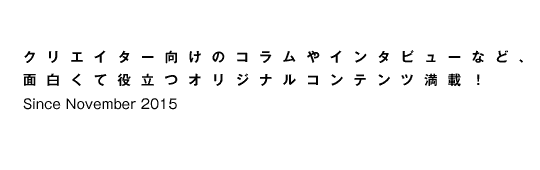●母ですらない
初めての出産を経験して1ヶ月が経つ。生活が大きく変わり、「こんなの聞いてなかった」案件の連続で立て込んでいた。特に授乳に関する戸惑いはこの先ずっと忘れないと思う。
赤ちゃんが柔らかい乳房を小さな手で掴み、うっとりした様子でおっぱいを飲んでいる。そんなイメージは作られたものだと知るのは出産直後のことだ。むしろ私にとって授乳は、これから何年も続く育児の最初の大きな関門だった。まずそれまで性的なシンボルだった乳房が、突然赤ちゃん目線に切り替わる。産院では吸いやすい乳房と、そうでない乳房に分類された。どうやら私の乳房は少し吸いづらい類らしい。赤ちゃんもおっぱいを飲むのに慣れておらずへたっぴだ。本能の力で飲むものだと思っていた、ついこの間までの自分は無知でしかない。
空腹で泣く我が息子のために乳房を近づけると、「欲しいのはこれじゃない!」と言わんばかりに顔を真っ赤にして更に泣きじゃくり、小さな手で力いっぱい乳房をはねのける。私は何とか口に含ませようと必死に手で補助をする。歪に力が入って身体が痛い。乳房を拒否されると、母としての自分が拒否されている気がしないでもなく、じわりじわりと傷ついた。そういう訳ではないと頭では分かっていても、だ。産後3週間はこれを毎日合計7時間ほど繰り返していたので、憂鬱で仕方なかった。
神話的イメージとかけ離れた、苦しい授乳の時間。私のような迷える女性のために、次の答えが用意されている。つまり未熟な母子が授乳の練習をして徐々に上手になる、その過程で二人の絆が深まっていくというのだ。でも、でも、と私は思う。なんだか出来すぎじゃないかと。
まだ「母」ですらないのに。
彼をこの上なく愛おしいと思う一方で、しかしまだよく知らないという気持ちが私の中で同居している。「母」という肩書に居心地の悪さを感じる自分がいる。だって私たちは出会ってからまだひと月しか経っていない。たとえ生物学上の親子であっても、つまるところ他者同士である。生活の中で柔らかい皮膚の感触や、吐息の体温を感じながら、お互いの存在をそれぞれのやり方で確かめ合っているところなのだ。
この社会には母子のための物語がたくさん用意されている。でもそれらは私や彼のために作られたものではない。むしろ毒になることだってあり得る。私は、私(とパートナー)が与えた名前で彼を呼ぶ。そのうち彼も私のことを「お母さん」と呼ぶだろう。そこにはいつだってことばの境界線のせめぎ合いがあるはずだし、あって欲しいと、窓から差し込む光で透ける彼の胎毛を見つめながら思う。

▲使用機材はすべてCANON 5D MarkIII。(クリックで拡大) |
 |
|

▲(クリックで拡大) |
 |
|

▲(クリックで拡大) |
 |
|
次回は林朋奈さんです。
(2023年3月9日更新)
●連載「女子フォトグラファーの眼差し」のバックナンバー
第33回~
第1回~第32回
|