 |
|
鈴木心/すずきしん
1980年福島生まれ。東京工芸大学芸術学部写真学科卒業。アマナに勤務後、独立。現在フリーランス。銀閣寺同仁写真部部長。広告、雑誌の写真制作、CM、PV などの映像制作をする傍ら、自身の作品の制作発表を行っている。2005年第24回ひとつぼ展写真グランプリ、2005年キヤノン写真新世紀佳作/森山大道選。写真集に「写真」ブルーマーク(2008年)、「高良健吾 海 鈴木心」赤々舎(2011年)がある。
仕事に関するポートフォリオ:http://suzukishin.wipe.vc
|
| 取材協力:アドビ システムズ 株式会社 |
Profile & Works

 
▲大学4年次の頃の作品。だんだんと自分の表現したいことに技術が伴ってきた時期(クリックで拡大)
|
 |
 
▲必ずと言ってよいほど三脚をつけて撮影をしていた。シャッタースピードの制限から解放される(クリックで拡大)
|
 |
 
▲水平垂直とピント位置と深さへの配慮を徹底的に行う(クリックで拡大)
|

●バンドと写真の学生時代
−−まず、写真家になられた経緯をお話ください。他のインタビュー記事で、高校卒業後2年はバンド活動をされていたと読みました。
鈴木:高校卒業後は音楽をやりたくて、地元でバンド活動をしていました。幼稚園からピアノをやっていたのですが、当時はギターを弾いていました。ただ親には「20歳になっても無職だったら自活しろ」と言われていて、結果新しい一歩を踏み出すきっかけになりました。
成績が良くなかったので、大学の偏差値ランキングの下から見ていって、美大なのにランキングが低いところを見つけて、それが東京工芸大学だったんです。当時地元でもAPSのコンパクトカメラで友達を撮っていたので、飽きっぽい僕には写真は手間がかからないと思い専攻しました。それくらい軽い気持ちだったので、大学入ってからも、プロとアマチュアの写真の違いも分からなければ写真家すら知らない程度でした(笑)。
大学の授業で、暗室を使ってフィルムの現像の実習があったのですが、被写体が家の近所の風景など何を撮ってよいか分からなかったので、友人と原宿に行って自分が可愛いと思う女の子に声をかけて写真を撮らせてもらっていました。
そうすると、どんな写真が撮れているのか気になるので、すぐ現像したくなるじゃないですか。そんなことを毎週やってたんですね。そのうちに原宿では飽き足らなくなって夏休みに電車で全国を回ったんです。全県の可愛いと思う子を撮ろうと。その頃から、写真って面白いかもなと思いはじめました。大学でも音楽サークルに入ってバンド活動をしていたのですが、あれよあれよとクビになり、自ずと写真に絞られていきました。
−−最初はミュージシャン志望だったのですね。
鈴木:そうです。今でも若干残ってはいますけれど。音楽家の知り合いなどの姿を間近で見るともういいかなぁと、思うこともあります。
−−音楽ではアメリカのレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンが好きだったとか。
鈴木:なぜならば社会的主張を組み込んだ音楽だったからです。人種差別、大企業の搾取、歴史的な国家的犯罪などに対してのメッセージを音楽に取り入れることで、社会的な行動となるバンドの模範として、面白いと思っていたんです。でもその一方でフリージャズが好きだったので、理論や技術を突き詰めることができるかに興味を持っていました。
僕の写真のスタンスは音楽から来ている部分が多々があります。当時は動画投稿サイトなどもなく目の前で演奏してくれる有名なミュージシャンなどいないので、CDなどを聴きながらどうやってこの音を組み立てたのかを想像しながら弾いてみる。それは写真も同じで、カメラマンの撮影作業自体は見ることができないから、出来上がった写真を見ながら、どうやって撮ったのかを想像して、自分でも模倣してみる。音楽と同じ考え方をそのまま写真に当てはめてみただけなのです。

 
▲大学1年次の時のスナップ群からの1枚(クリックで拡大)
|
 |
 
▲当時大学に通っていた厚木から毎日都内に出て撮影していた(クリックで拡大)
|
 |
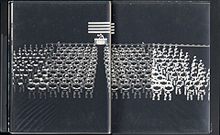 
▲当時から被写体は人物、物、風景を問わない構成でブックを頻繁に作っていた(クリックで拡大)
|

●作品としての写真
−−鈴木さんの作風は広告からドキュメンタリーまで幅広く、これが鈴木さんの写真だというイメージを持ちにくい気がします。ただ、どんな被写体に対しても一定の距離感を感じますね。
鈴木:そうですね。こういう時代なので、後で加工・修正することを前提に素材として写真を捉えることもできるのですが、僕には、現実に対して生(なま)な形で強力に見せることができるかどうかがとても重要です。つまり後付けの効果ではなくて素の写真である必要性をどれだけ高められるのか、写真の素のポテンシャルを出せるかどうかなのです。特にプライベートな作品作りにおいては最重視しています。
ですから、デジタルだろうとフィルムだろうとできるだけ加工はしないで、撮影もJPEGで、シャッターで完結させる。写真という必然性の一番単純な動機を最大限に拡張した考えです。そうでなかったら、今は絵でも3D CGでもよくなってしまう。そこにはずっとこだわってきました。
−−影響を受けている写真家にprovokeの同人やマーティン・パーを挙げていますね。
鈴木:初期はそうでした。大自然の夕日や南国の写真など、大抵「美しい」という自然賛美主義で片付けられているものは昔からくだらないと思っていたのですが、そうじゃない撮り方、見せ方を彼らから感じて、こういうアプローチもあるんだっていうところから、だんだん写真が面白くなってきました。
−−自然の切り取り方とか目線とか?
鈴木:もっと思想的な面です。反体制的で、写真という表現に対して、どれだけ写真でありながら写真ではないものを作るのかを徹底した表現だった。社会体制に対する反感と、写真という体制に対するアンチテーゼがリンクしていた。そういうラディカルなスタンス、先程のレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンもそうですが、表面的な表現ではなく確固たる意思の元に表現されているものに共鳴しました。
−−基本的に鈴木さんの表現者としての立ち位置というのは、世の中を一歩引いて見ているような、少なくとも肯定の目線ではないですよね。
鈴木:というよりも、体制や主義はひとくくりにできるような状態ではないですよね。例えば3人集まれば、3人まったく同じ思想にはならない。そこをひとくくりにして、じゃあ資本主義にしますというのを、何億人単位でやってるわけじゃないですか。それでうまく経済的に運営するために教育を施して作った社会という形式が、そもそも人間と言う動物に対して無理があるシステムなんだと思います。
社会を包括しているもの、そして体系的なものに興味があります。例えば学校には学校の、秩序を持たせること以外に意味のないルールがあります。経済、社会、地球、宇宙とかそういう体系のなかで自分が存在していることを理解をしつつ、現実に臨んでいかなければならないのです。僕は写真によって見えるものに向かいながら、実際には見えないその成り立ちを想像し、それをまた写真によって表現するように務めています。
−−いわゆる見て美しいもの、構図的に美しいものを目指す視点とはまた違うスタンスですよね。
鈴木:違います。チャンネルとしてそういうものは理解しているので、撮ろうと思えばいくらでもできるのですけれど、それはたくさんの他の人がやっていることなので興味はありません。
「美しい」というのは体制的な感覚ですが、美しくないものから美しいものを提案できるのは反体制的ですし、新しい解釈とも言えます。それをどうやって体制の中にいる人たちにうまいバランスで人間の価値観として新しく芽吹かせらせるかという提案を行うことが、僕にとっての課題です。
−−なるほど。新しい価値の提案を写真によって行う。ある意味表現者としての基本的なスタンスなのかもしれません。ちなみに、10代の終わりに写真の道を選んだということは、当時は、食うためには写真かなという考え方だったのですか。
鈴木:当時は写真で生計を立てることは考えていませんでした。自分の好きなことが音楽から写真に移っていったという感じで、職業として意識したのは、大学4年からですね。将来どうしようかと考えて、写真でもいいかなぁと思いました。

 
▲大学3年次に大型カメラで撮影していた建設現場の写真連作(クリックで拡大)
|
 |
 
▲多く東京の埋め立て地や地方の巨大な建築現場を撮影していた(クリックで拡大)
|
 |
 
▲撮影地は一番左の写真がお台場、中央が有明、この写真が御殿場。現在はすべて完成している(クリックで拡大)
|

●プロの技能を身に付けたアマナ時代
−−大学を卒業された後は、広告写真制作会社に入社されました。
鈴木:大学3、4年で6つくらいのコンペで賞をいただいたので、すぐにフリーになりたかったんです。4年の夏に友達からアマナという会社を教えてもらって、カメラマンになるんだったらスタジオマンになるよりそこにいくのが近道じゃないかと思いました。とにかく社会に所属したくなくて大学院に行くことも検討していたので、会社でのアシスタント経験を大学院として考えることできるのではないかと思って応募しました。それが2月くらいで、広告写真のことを何にも知らずに面接に行って「大きい仕事をしたい!」と(笑)。だから入社した動機は仕事より勉強の方が強かったです。そんな状況だったので、仕事も広告業界のこともイチから勉強しました。
−−会社での仕事内容はどうでしたか。
鈴木:僕は1年アシスタントをして、その後2年弱カメラマンでした。
−−新卒2年目でカメラマンは出世ですよね?
鈴木:そうです。かなり早い部類でした。すごく皆様に面倒を見ていただいていたので逆にものすごくプレッシャーになり、少しでも早く結果を出したいといつも思っていました。
−−学生の頃に賞を取っていたので、そういった経歴も評価されたのでしょうか。
鈴木:受賞歴より面接時にたくさんのブックを作って持参したので、写真への意欲をかっていただいたと思っています。ですが写真における主軸はあくまで自分の作品の制作と考えていたので、普通の会社員として長く活動していこうとは思っていませんでした。
−−広告写真は商業主義な写真が中心で、鈴木さんの表現者としてのスタンスと相反すると思うのですが、写真家として広告写真のノウハウや技能を身に付けたいという考えがあったのですか。
鈴木:技術はできる限り身に付けたほうがいいと思っています。出来るのにやらない、ということと、出来ないからやらない、ということは結論は同じでもまったく違います。僕は写真というのは職業でもあるので技能を身に付けておいて使わないという方がさまざまな状況に対応できると考えました。さらに多くの広告写真家は技術には長けていますが表現の確信が薄いということも気付いていました。つまり技術で確信を暫定的に補完することもできるのです。
−−では、会社でそういった高度な撮影技術を得られたのですね。
鈴木:そうですね。会社の教えとして、ホテルマンのように細かい配慮に気がつけるサービス意識を持てというものがありました。商業写真を撮っていく上で、写真の品質も当然大切ですが、結局はクライアントも人間ですので人と人のコミュニケーションなのです。例えばちょっとした掃除や配膳など人に対する気遣いを学べたのも非常に大きかったです。
またデジタルワークフローやオペレーションもこの時期に学びました。本当の意味でのPhotoshopとの出会いです。今でもそうですけれど、現場でレタッチャーと一緒に仕事をして合成の工程など何度も目にして学びました。
−−鈴木さんは当時から広告と自分の作品と両面で活動されています。仕事では技術を駆使し、作品では技術は捨てる、その2つのアプローチにご自身の中で矛盾はありませんか?
鈴木:クライアントのためか、自分のためか。それが混在するのが一番自分の中で気持ち悪いんです。その2つが良い循環になっていて、広告仕事などを詰めていく過程で自分の作品のヒントをみつけたり、自分が好きでやっているなかで仕事のヒントをみつけたりする、その循環で新しいことを発見してきました。

 
▲アシスタント時代の作品。仕事を想定した撮影とレタッチの模擬訓練のようなもの。もちろんモデルは自分たち自身(クリックで拡大)
|
 |
 
▲必ずレタッチャーと作品を作ることを心がけていた(クリックで拡大)
|
 |
|

●見たままを撮る。フリーダウンロードの写真。
−−鈴木さんは作品をホームページからフリーダウンロードできるようにしています。その写真群は自由気ままに撮影している印象があります。
鈴木:広告写真など、レタッチで修正・合成を詰めて精度を上げていくと、写真ってどれも似てくるんです。撮影はある意味数式のようなところがあるので、建築には建築の、広告には広告のセオリーがあります。そのコツを技術的に落とし込めば大抵の問題は解決できます。しかしそれをどこかで自分で解体していかないと先に進めないので、プライベートの写真に関しては、目に入ってきたものすべて撮ってもいいんじゃないかというくらい無作為にしています。少しでも構図を考えた時点で精度が上がってしまうので、これは仕事とはまったく別のものという認識です。
それと技術的にではなく、観念的にデジタルって何だろうということを追求したいです。デジタルはフイルムや印画紙がいらないのでお金が掛からない。ですから写真を量という面からも徹底的に追求できると思います。携帯電話に埋め込まれているカメラが有料だったら皆使うでしょうか? 否、無料だからこそ、写真を撮るという行為が尋常じゃないスピードで広まったわけです。かつてそういった条件はありませんでしたから、この部分だけでも写真における新たな観念が見えてくると思っています。
さらに僕は圧倒的な量と圧倒的な高解像度を組み合わせることに興味を持っていて、昨年9月に買ったカメラで1年間で7万枚か8万枚くらい撮ってみました。仕事においてはまだしも、それを公開してフルサイズで自由にダウンロードできるようにしたというのは稀なのではないでしょうか。中判デジタルのPhase Oneも使いながら、まだまだ続けたいと思っています。
−−そういった行為に対する答えは、まだ見えてきていないということですか。
鈴木:はい。時代の移り変わりなどで本当の理由は大分後で見えてくるものだと思います。
−−歩いて撮っている写真もあれば、車の中から撮っているものもあります。それに夜の写真などはノイズも気にされていないような感覚で撮影されていますが、ノイズは写真の本質には関係ないというお考えですか?
鈴木:そうですね。振り返ればフィルムのときからノイズ(粒子感)は乗っていたので、ノイズを消そうという考え方がレタッチで粗を消す感じにすごく近いと思うんですよ。ノイズといってしまうから受け入れにくいのであって、それも1つの写真の要素だと認識しています。
−−ノイズって基本的には装置の出力の一部で、限界が見えてしまっているから隠したいというのが通常の認識ですね。
鈴木:僕はこの時代の技術的限界もそのマシンによる写真という出力の一部ですから、収めておいてよいと思います。写真はいつの時代もハードに依存している表現なので、ノイズもいずれ技術が進化してなくなっていくのであれば、現状を受け入れる考え方の方が健康的だと思います。
| page 02|
|




