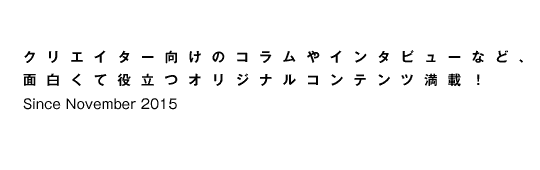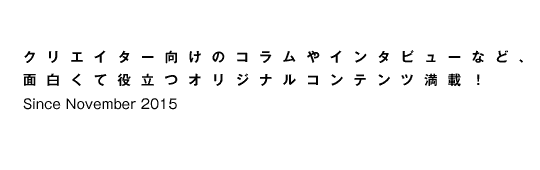●「写真」と「AI」のハイブリッド作品
私はこれまで写真家として、また美術家としてさまざまなタイプの「写真作品」を制作して来たが、今回は生成AIによる作品『ニッポンのうれしい場所』をご覧いただこうと思う。
これは基本的に日本の観光地を撮った「写真」なのだが、そこに写る人物の「顔」だけをPhotoshopの生成AIで別人に変換している。つまりこれは写真の一部のみをAIで変換した、写真とAIのハイブリッド作品と言えるのだ。

『ニッポンのうれしい場所』より。(クリックで拡大) |
 |
|
●伝統的な「人物スナップ」と肖像権の壁
とは言え、この作品はあらかじめAIで変換しようと思って撮り始めたわけではない。ことの発端は、コロナ禍明けで久しぶりに自宅のある神奈川の山間部(秦野)から、新宿の繁華街に出たことだった。
この時、街中に夥しい数の外国人観光客があふれていることに驚き、しかもみな一様にうれしそうな顔をしており、私自身もうれしくなってしまったのだ。
そしてこの状況をぜひとも「写真」に撮りたくなったのだが、この時持っていた撮影機材がSIGMA fpという35mm判デジタルカメラと、Ultra Wide Helier 12mm F5.6というレンズの組み合わせだった。このUltra Wide Helier 12mm F5.6は、画角が122°もあるその名の通りのウルトラ広角レンズで、こんなもので撮った「人物スナップ」を私は見たことがなかったが、それだけに「実験」も兼ねて撮影してみた。
そうしたところ、自分が意図したイメージが、思った以上にリアルに表現され、これはイケる! と思ったのだ。ところが一方、今の時代は「肖像権」の行き過ぎとも言える主張が蔓延した結果、伝統的な「人物スナップ」が発表しづらい風潮になっている。

『ニッポンのうれしい場所』より。(クリックで再生)) |
 |

『ニッポンのうれしい場所』より。(クリックで拡大) |
●Photoshopに追加された「生成塗りつぶし」機能を試す
と、思っていたところ、ふと写真に写る人物の「顔」だけをPhotoshopに新しく装備された「生成りつぶし」機能を適用してみたらどうだろう? と言うアイデアが閃いた。「生成塗りつぶし」とはPhotoshopに新しく追加された、独自の生成AI機能で、写真の一部を選択しそこに無いものを加えたり、逆に邪魔なものを消したりもできる。
この機能は「人間の顔」について特に何も謳ってなかったが、ダメ元で試してみたところ、選択した「元の顔」が違和感なく「架空の別人」に変換されビックリしてしまったのだ。もちろん単純な顔ハメではなく、写真に写った人の性別、年齢、人種、表情などきちんと踏まえながら変換し、さらに光の当たり方やパースの歪みに合わせ「写真」として違和感なく仕上げてくれて、技術の進歩に感心してしまった。
とは言えAIは100%完璧ではなく、そのため変換候補が3パターンずつ生成されるから、そこから自分の意に沿った顔を選んでいく。時にはトンデモなく気持ちの悪い画像が生成されることもあり、そんな場合は選択範囲を変えたりプロンプトを加えたりと、意外と人間側にコントロールする余地があり、そうやって「自分の作品」へと仕上げていくことができるのだ。

Photoshopに追加された「生成塗りつぶし」機能。(クリックで拡大) |
 |
|
●ZINEと個展の連動で作品を発表
このように一定の方法論を確立した私は、新宿のほか浅草、上野、原宿などに赴いて撮影し、2024年5月にその成果を『ニッポンのうれしい場所』と題した個展で作品集(ZINE)として自費出版し、同名の写真展を水道橋の「路地と人」というスペースで開催したのだ。
そうしたところ、写真家をはじめとする多数の方々にご来場いただき、「顔だけ生成AI」と言う手法や「肖像権問題」に一石を投じた点など評価していただき、私としてもホッとしたのだった。ZINEの出版も自分としては初めてで、編集デザインもすべて自分で行ったが、おかげさまでネット通販も含めて完売し、二刷りを増刷することになった。
●ハイブリッド作品から見えてくる「写真」と「AI」の関係
さて、あらためてこの『ニッポンのうれしい場所』と言う作品を考察してみると、「写真」と「AI」のハイブリッドだからこそ、その両者の関係が見えてくる。
まず、私もそうなのだが「生成AI」という新技術を前にして思うのは「何でも生成できるだけに、何を生成させたら良いのか分からない」ということで、途方に暮れてしまうのだ。しかしそれは「写真」も同じで、写真は何でも撮れるだけに「何を撮って良いか分からない」し、逆に言えば「何をどう撮るのか」によって写真が「作品」になるわけで、それでずいぶん悩んだ時期が私にはあった。

『ニッポンのうれしい場所』より。(クリックで再生)) |
 |

『ニッポンのうれしい場所』より。。(クリックで再生) |
●アルゴリズムの学習は、AIも人間も同じ
そもそも「良い写真」とは何か? を考えてみると、今はスマホを含めカメラが高度に進化した結果、誰もが簡単にキレイな写真が撮れるようになったが、とは言え誰もが「良い写真」を撮れるわけではない。それが可能となるには「才能」よりもむしろ「経験」が重要で、実際に自分で写真を撮ると同時に、SNSにアップされた「良い写真」のみならず、歴史的に「名作」とされる写真家の写真を数多く見ることで、「良い写真のアルゴリズム」がだんだんと学習できるようになる。
さらに絵画や映画、音楽や小説など、さまざまな分野の「良い作品」に触れながら「良い作品のアルゴリズム」の学習を重ねることで、さらに「自分らしい写真」が撮れるようになるのだ。
私の場合を言えば「写真」の原点を葛飾北斎の浮世絵に見出し、実家の近くにある「北斎館」(長野県小布施町)で作品を繰り返し鑑賞しながら「遠近法の妙」というアルゴリズムを見出し、それは強烈な遠近感を描き出すウルトラ広角12mmレンズの撮影にも活かされている。
このように「膨大なデータから特有のアルゴリズムを読み取って学習する」と言う点で「人工知能」と「人間の知能」は本質的に同じだと考えることができるし、だからこそ「人間の知能」をより豊かに育てることによって、その延長の「生成AI」もより良く使いこなせるようになると、考えることもできるのだ。

『ニッポンのうれしい場所』より。(クリックで拡大) |
 |

『ニッポンのうれしい場所』より。(クリックで拡大 |
●「世界の生成」に向き合うのが「写真の本質」
さらに考察を深めると、そもそもAIが「バーチャルな現実」を生成するはるか以前から、われわれの「リアルな現実」そのものが、時間とともに「生成」され続けている。私の『ニッポンのうれしい場所』にしても、コロナ禍で人がほとんどいなくなった街中に、忽然と大量の外国人観光客が、以前にも増して「生成」されることの驚きが、撮影の動機になった。
これに限らず「良い写真」を撮る人は、誰もがそれぞれの立場から「世界の生成」に立ち会っていると言えるし、それこそが「写真の本質」の1つではないかと思うのだ。そう考えると「生成AI」と言う技術そのものが「生成された新たな現実」の一部であり、その観点から「写真」との関わりを考える価値は十分にある。

『ニッポンのうれしい場所』より。(クリックで再生) |
 |

『ニッポンのうれしい場所』より。(クリックで拡大) |
●「写真の黎明期」から考える
「AIの黎明期」の可能性。もちろん、生成AIは近年になって突然現れた、人類にとってまったく未知の技術には違いなく、それによる不安や恐怖が生じるのも「人間の知能」の自然な心情だとも言える。
しかしそれは19世紀に「写真術」が発明された当初も同様で、特に画家たちは「写真」の登場に不安や嫌悪感を持ち、実際に多くの肖像画家たちが失業に追い込まれた。一方で写真の黎明期は「肖像写真」「風景写真」「報道写真」「科学写真」「ファッション写真」「芸術写真」などあらゆる写真分野の黎明期でもあり、前例のない中でパイオニアたちのクリエイティビティが如何なく発揮された、もっともおもしろく、また熱い時代だったと言えるのだ。
と考えると、今はまさに「生成AI」の黎明期で、もっとも不安定で不安な時期だからこそ、各自がそれぞれの仕方で「人間の知能」を育みながら「生成AI」の可能性を追求する価値があるし、いずれにしろ我々はあらゆる意味でトンデモない時代を生きていると言えるのだ。
次回のコラムは澤村 徹さんの予定です。
(2025年4月11日更新) |