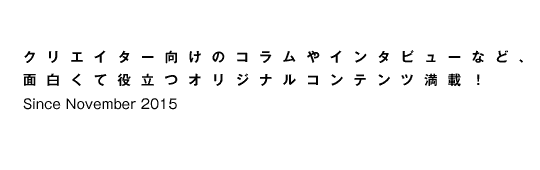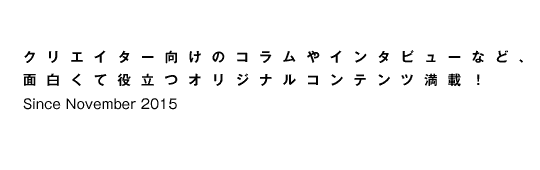撮影機材:Canon EOS M3。以下すべて同じ。(クリックで拡大)
|
 |
|

(クリックで拡大)
|
 |
|

(クリックで拡大)
|
 |
|

(クリックで拡大)
|
 |
|

(クリックで拡大)
|
 |
|
●見ようとしないと見えない
「暗い写真だね。」「なんかネガティブー。」「魔女みたいな人が撮ってるのかと思った。」とよく言われる。満更でもない。わたしはそういう人間だからだ。
オレンジ色の光が斜めに視界を舐める時間、不承不承外に出た。足には踵がすり減り始めたスニーカー、手にはわたしの指の熱で変形したカメラ。写真を撮るのは毎日のことだ。アイフォンにイヤフォンを刺す。ギター音が入ってきて、生温かい煙が出ていく。
陽の光が眩しい。それはキラキラしたものではなく、攻撃にすら感じる。足下はコンクリートの海。どこまで行っても東京。薄皮が剥がれて鉄の味がする唇を噛み、乾いた海を蹴る。
環七にまとわりつく排気ガスのざらついた匂いは嫌いじゃない。見慣れたコンビニを追い抜く。写真を撮りに出る時は目的地を決めない。ひたすら歩く。目的は見ることだからだ。わたしの場合、見るというスイッチは意図的に押さないと勝手には入らない。見よう、と覚悟を決めて、見るということに集中する。
シャンとした足音が2メートルの距離のまま付いてくる。また追い抜く。今度は息を止めて。しばらく経って、劣等感が追いかけてこないことを確認し、振り返った。突然独りの冷たい温度が漂う。わたしの音だけ。
深く息を吸い込んだ。首から上だけの白椿が照らされてる。弔いのスポットライト。そういえば紫陽花の終わりは、落ちるでも散るでもなく、零れると言うらしい。静かにずっと見ていた。最期は落ちた方が楽だろうか。わたしは零れたいと思った。
ある日は雨上がりだった。踏み潰されたわたしを振り返る人はいない。たらりと流れ続ける言葉はヒンヤリと痕になり、あの日の「どうして、」は消えないままだ。
ある日もわたしは東京にいた。ふと気づいたことだけれど、目的地は決めないと言いつつも、わたしは虫と同じように光の方へ向かう傾向があるらしい。光に憧れ吸い寄せられていたら「ほら、あなたは影にいるからだよ。」と何処からか声が聞こえた。
時は命だと何かで読んだ。
シャッターで時を刻む度に生きている実感が湧く。というのはカッコつけすぎだろうか。
この身体が細胞分裂を続けている実感も、赤い液体で充満している実感も、まるで無い。ところが日に日に皺だらけになる外殻を荷物に、わたしという存在がサラサラと渇いていく感覚はあるのだ。何の為に生きているかもわからない日に、シャッター音がわたしの目を覚まし、ギリギリのところで狂わずにいさせてくれている。目の前の存在を捉えることでわたしの存在が浮かび上がり、一滴ずつ滲んで色になる。
見ると生きるは似ている。見えていると見るが違うように、生きていると生きるは違うものだ。
とにかく能動的に、感度を高くして瞳孔を開く。そうして生きないと見えてこないものが必ずある。
季節がゆれる。花が咲く。晴れてきた。出会い。これから。ありがとう。あの人の存在。
それを絡め取って胸の真ん中に押し込み、溶かしながら体液と撹拌し、それをエネルギーに自分を楽しませてやることが、生きるということなのではないか。フォーカスしなくても勝手に写りはするけれど、写真にはならない。突然のシャッターチャンスをものにする人は常にそれを探していて、幸せは感じようとする人に訪れている。そしてそれは誰かを幸せにしようとする人だけに。
その刻んだ産物の穴からはすべてが漏れ出てしまっていた。劣等感も、孤独も、欲望も、絶望も、昨日の後悔をしているわたしも、写っていた。それは叫び出しそうなくらい恥ずかしいことだけれど肯定するしかない。それでいい。
それでいいのだ。ずっと続けてきたのだから、これからも続けていく。
排気ガスに塗れ、虫のように光を求めて、わたしはわたしにしかなれないと思い知るけれど、ここから見えるもの、見えていたもの、すべてが愛すべき存在なんだと、大丈夫だからと、分身が背中を押す。感度を高く、生きていきたい。幸せになりたい。誰かの役に立ちたい。できることならば。
わたしは薄い皮を噛みちぎり、何度でも繰り返す。今日も東京で。サラサラと少しずつ零れながら。
次回は福尾美雪さんです。
(2020年2月14日更新)
●連載「女子フォトグラファーの眼差し」のバックナンバー
第33回~
第1回~第32回
|