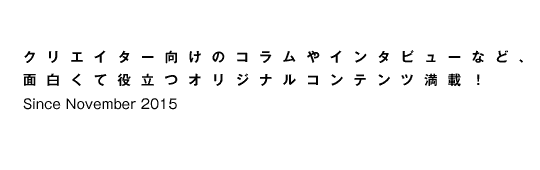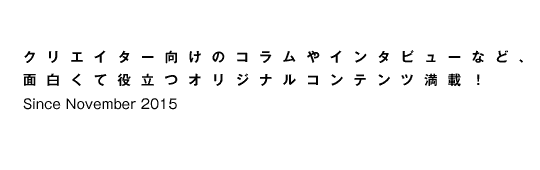|

▲2016年11月、山形県東根市
(iPhone 6で撮影) |
 |
|

▲2016年11月、山形県東根市
(iPhone 6で撮影) |
 |
|

▲2016年11月、山形県東根市
(iPhone 6で撮影) |
 |
|
●虚構がリアリティになるとき
11月、2週間にも満たないが田舎に帰省している。晩秋、木々は葉を落とし、りんごの収穫の終わった果樹園は灯が消えたように見える。当たり前のことだが、ここでも多くのものが失われたり、変化してしまった。消えてしまったものたちとは、どうすれば再び会えるのだろうか。
私は奥羽山脈の麓で生まれ育った。小学校を出るまでは曾祖父母もいる4世代同居の家で育ち、曾祖母や祖母とも長い時間を過ごした。戦前のみならず、大正や明治の記憶がまだ影のように生き残っていた場所が私の故郷だ。
人間を化かす狐やムジナ、鬼火、先祖や村の人々の悲劇的な話など、何世代前から引き継がれたのかも分からない昔話をよく聞かされた。辻々に置かれた小さなお宮やお地蔵さんは、気軽に手を合わせる身近な存在だった。毎朝水と炊きあがったばかりのご飯を供える仏壇は、先祖という死者たちと日々向き合う窓だった。
こんな風に育った私が海外に住むようになって、もう足掛け20年になる。理性と明解さ、ロジックと合理性が支配するオランダにいると、自分の東北のルーツがますます自分の写真表現に影響を与えていると感じる。2011年の震災の後はことさらそうだ。
オランダの日系人たちという被写体に出会うまでは、オランダでは何にも写真が撮れず、スタジオに作った建築模型を暗闇の中で撮影していた。日本では今でも帰省の度に幼少時の記憶をたどりながら、故郷を歩いて写真を撮っている。このような写真は今現在のリアリティを反映していないかもしれない。しかし写真に撮ることによって、特にフィルムにイメージを焼き付けるという行為によって、すでに消滅したものたちや私の子供時代の空想の中だけに存在したものたちがリアリティとして蘇ってくる。
次回は富谷昌子さんです。
(2016年12月7日更新)
●連載「女子フォトグラファーの眼差し」のバックナンバー
|